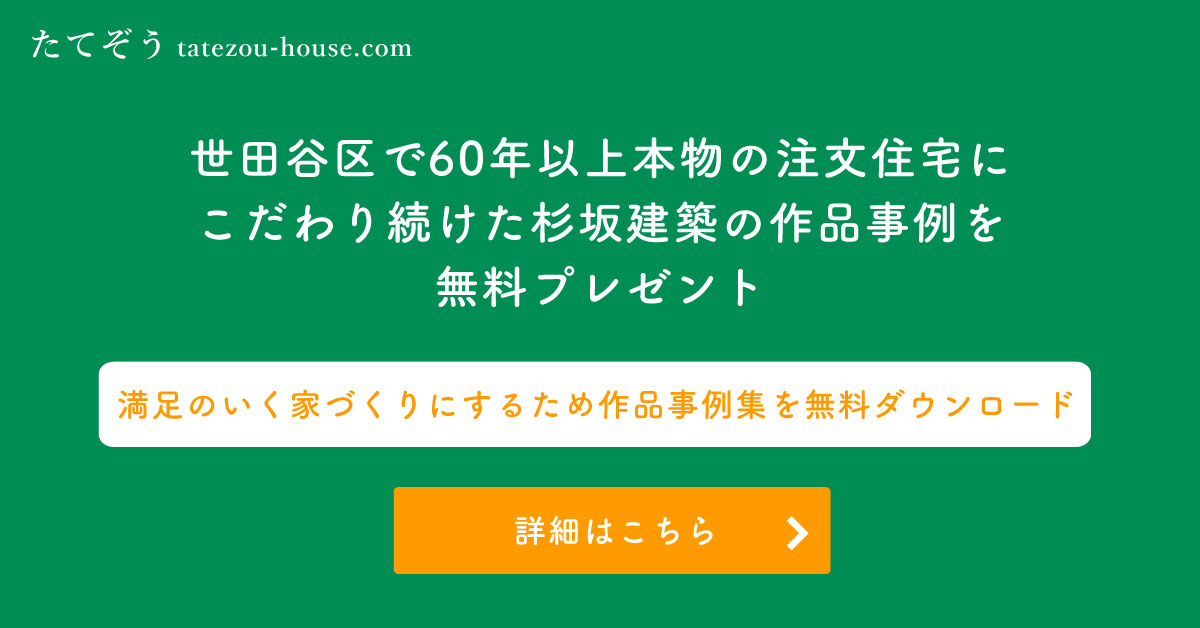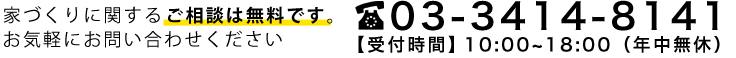平屋だけれどプラスアルファのスペースとしてロフトが欲しい。でも、実際使い勝手はどうなのだろうかと気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
平屋建て住宅の場合、同じ面積の2階建て住宅と比べて屋根面積が大きくなります。
そのため、天井裏のボリュームも大きく、ちょっともったいない感じもします。
ですが逆にこれは未利用空間が多分にあると言い換える事も出来ます。平屋建て住宅は、部屋の上半分を使ったロフトスペースを追加し、様々な用途に活用できる可能性に満ちているのです。
今回はこの平屋においてロフトや小屋裏空間を検討する際のメリット・デメリット、そして間取りや設計の考え方についてお伝えしますので、ご興味のある方は参考にしてみてください。
1 ロフト・小屋裏収納の考え方
 平屋建て住宅は全ての要素が1階に集中するため、当然部屋数に比例して床面積が広くなります。従って、(これは建物形状によっては必ずしも全てに当てはまりませんが)シンプルな形で屋根をかけようとすると、大きな屋根裏空間が出来ます。
平屋建て住宅は全ての要素が1階に集中するため、当然部屋数に比例して床面積が広くなります。従って、(これは建物形状によっては必ずしも全てに当てはまりませんが)シンプルな形で屋根をかけようとすると、大きな屋根裏空間が出来ます。
切妻屋根ならば家のほぼ中央部で最も高低差が大きくなる事が多いです。そしてそこに生まれるスペースも大きくなり、居室としても使えそうな気持ちになってしまいます。
しかし、だからといって安易に部屋を作ってしまうと、法律上その建物は平屋ではなくなり、2階建て住宅とみなされてしまいます。
2階建て住宅とみなされる居室を設けると、今度はそこに建築基準法上の規制がかかってきます。長時間過ごし易い快適な空間になってしまうと、その空間に対し様々な安全性を確保しなければならなくなるのです。そうすると建物の確認申請内容を変えるとともに、2階建てとしての構造上の配慮(計算)や避難上の安全性(ハシゴでは無く階段の設置など)、場合によっては採光・換気量確保のための窓設置など、なんだか変更が大げさな物に発展してしまいます。
建築費も大きく変わります。
そのため、多くの人はこの平屋の天井と屋根の間のスペースを、法が居室と見做さない範囲内とされる天井高1.4メートル以下に抑えた空間として設えます。

2階建てにして書斎スペースに
もちろん、「いっそ2階建てにしてしまおう」と方針転換しても良いでしょう。2階建てでしたら防火規制まで変わることはありません。上部空間を確保するメリットが大きいのなら切り替えてしまうのもアリです。個性的な空間に仕立てる事も可能です。
天井高1.4m以下のロフト・小屋裏収納に話を戻しましょう。
用途としては、普段は使わないものの収納場所や趣味のスペース、子供部屋の延長といった使い方があります。
なお、小屋裏と下の部屋が一体的に繋がっていればそれは小屋裏ではなくロフトとなります。建築基準法上はロフトも小屋裏収納も同じ扱いで、1.4m以下なら床面積から除外となります。容積率が一杯でもう少しスペースが欲しいときには助かります。
60年以上本物の注文住宅にこだわり続けた
杉坂建築のノウハウを見る
2 ロフト付き平屋のメリット
先述のとおり、ロフトを法律上居室扱いしないためには、天井の高さを1.4m以下にしなければいけません。1.4m以上の高さの部屋は居室であり、2階建て住宅に分類されてしまいます。
ただし平屋建て住宅の場合、天井自体の面積が広いので、天井が低くても広い小屋裏空間は結構有効に活用することができます。

リビングから直接小屋裏収納へ
ロフトや小屋裏のついた平屋を建てる場合の大きなメリットのひとつは、広めに取れる収納力。
日常生活で使用する頻度が少ないものであれば、ロフトや小屋裏に収納してしまうとスッキリします。
ロフト・小屋裏として確保可能な面積は、法的に下階床面積の1/2までとされます。
同じ面積の2階建てに確保出来る面積よりもだいぶ広いく確保できますし、物を持ちは運ぶ際も1階の上なのか2階の上なのかでエネルギーが異なります。
ほかにコストの面でもメリットがあります。
既に述べましたが、2階建てに仕立ててしまうと発生する要素が、平屋の基準を満たす範囲のロフトなら必要なくなります。
快適性の面では、小屋裏よりロフトにメリットがあると言えます。
どちらも居室としての快適性を与えるほどにならない小さな窓であれば設置可能です。だとしても、収納だけで無くちょっとした滞在空間としても使いたい場合にはロフト仕立てが良いでしょう。
小屋裏であってもエアコンは付けられます。そうすれば夏場をしのぐ事も出来るでしょう。但し天井が低く窓の小さな閉鎖空間はちょっと滅入りそう。それに対しロフトは開放的で、下の空間と一体の空調も可能ですから合理的です。
そうした事から、設計を工夫することにより多目的スペースとして狭いながら予備スペースとしても活用するロフトを選ぶかたが多いです。
具体的な使用方法としては、収納兼ホビースペース、子供が小さいうちの子供部屋、子供部屋上部の延長空間(就寝場所)など。
小学校の低学年程度であれば天井高1.4m以下でも十分に過ごすことができますし、寝る場所としてなら大きくなっても使えます。
このほかリビングの上空を大人が利用する書斎スペースとする事も。普段は天井の高いリビングに居て、集中したいときにロフトで作業という発想です。

このようにロフトを設置することはそれなりにメリットがあります。ではデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
60年以上本物の注文住宅にこだわり続けた
杉坂建築のノウハウを見る
3 ロフト付き平屋のデメリット
デメリットは、やはりその制限された空間という事が大きいでしょう。
収納力は高いものの人が直立できない天井高さや、大きく確保出来ない窓など様々な制限があるため、快適な空間にはなりません。
一般的な普段使いには向かない点はデメリットと言えるでしょう。
このほか、天井高さ1.4mに収まらない高さの物、重量や体積が大きくて持ち上げ困難な物も置く事が出来ません。

どうしてもそんな使い方や収納量を確保したい、というのであれば、先にも述べた様にロフトや小屋裏へ行くための固定階段を検討してみましょう。スペース的に難しい場合、急な階段になってしまう可能性もありますが、それでもある程度の幅としっかりとした固定感があると違うものです。
但し、固定階段は上部空間を快適にさせる要素の一つとも考えられます。このため自治体によって固定階段を規制している地域もありますので要確認です。
ハシゴで登るのは異空間へ趣く様な素敵な一面もありますが、せっかくの空間へ至る事が億劫になってしまうのも勿体ない事です。
60年以上本物の注文住宅にこだわり続けた
杉坂建築のノウハウを見る
4 間取り・設計の考え方
 ロフトも小屋裏も、建物の形状から屋根の一番高い位置が最もボリューム確保しやすくなります。
ロフトも小屋裏も、建物の形状から屋根の一番高い位置が最もボリューム確保しやすくなります。
こうしたことから、広いロフトを設ける部屋はリビング・ダイニングのほか多目的なホール状空間である事が多いです。
ロフトの直下は、天井がやや低くなってもそれほど気にならない台所や洗面・浴室などの水廻りや、和室などとする事が多い様です。
ハシゴ/階段どちらにするかについては、デメリットの項でも述べたとおり、使わなくなってしまわない様に、ロフトをどう位置づけるか充分検討する様にしましょう。

使用頻度が少なかったりハシゴにロマンを感じている方は、木製やスチール製のハシゴ等、お値段はしますが味が出て良いです。天井格納式のハシゴや架け外し可能なハシゴは軽いアルミ製がお勧め。省スペースで費用も抑えられます。
スペースが取れるからという安易なことで決めず、家族でよく相談することが大切です。
60年以上本物の注文住宅にこだわり続けた
杉坂建築のノウハウを見る
5 まとめ
建物の大きさや形状によって屋根の形は変わりますが、基本的に屋根をシンプルにかけると、平屋ならほとんどの場合中心付近に部屋になるくらいの面積が取れるので、上部空間の有効活用が図れます。
ロフトは開放感があって使い道のバリエーションも考えられるなど魅力的です。
小屋裏も含めて登り降りのし易さは使用頻度に関わりますので、ハシゴにするか階段にするかについては法規制を確認しつつ費用と共に検討してみると良いでしょう。