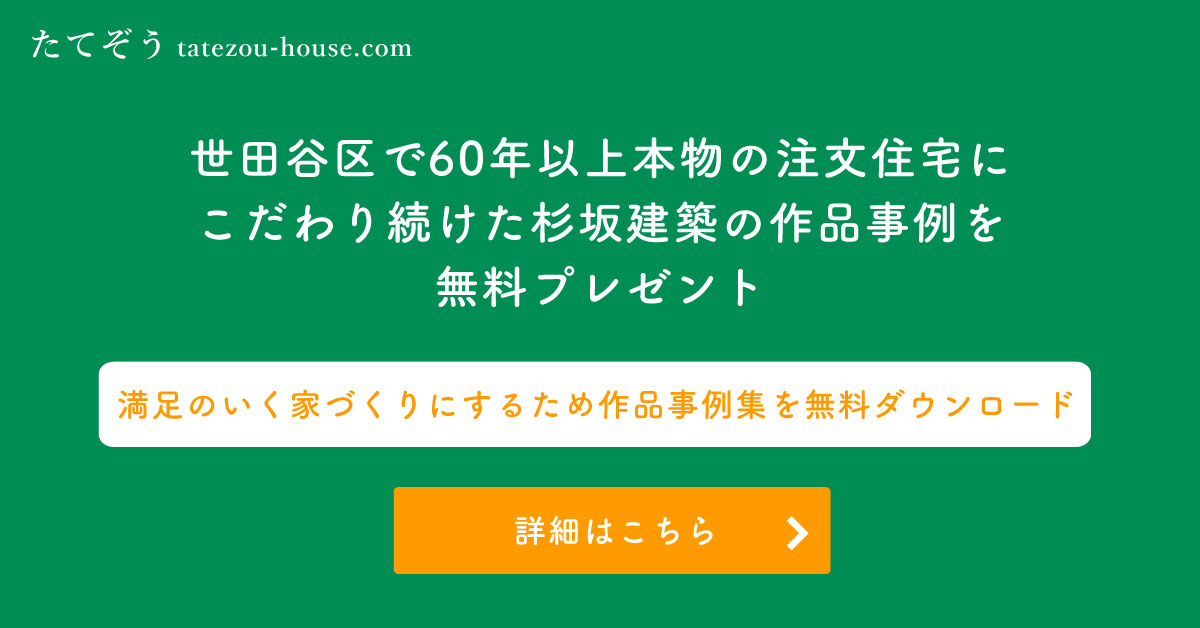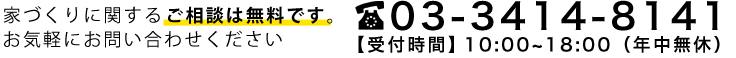昨今、都市部においては社会情勢、相続等の影響により土地が細分化され、需要と供給のバランスからか30坪程度に設定して売り出されるのをよく見かけます。
コンパクト過ぎず無理のない規模の住宅を考えた場合、一般的に30~40坪が一つの目安となることも多いのではないでしょうか。
若年世帯にとってみると、資金との兼ね合いで30坪の家を建てるという選択もあるでしょう。
また団塊の世代が定年を迎え、第二の人生を考える時代が到来してしばらく経ちました。これからを考えた夫婦2人の住まい、または一定の年代に達した若世帯との分離型二世帯住宅といった場合、世帯ごとに30坪台を目安として検討することも多くなっています。
さて、今30坪の間取りを考えようとしている方。ちょっとお待ちください。
間取りよりも先に考えなければならないことがあるのです。
今回は30坪の「平屋」においてどう考えるべきかについてお伝えします。
間取りに悩みはじめている方は後悔のないよう、ぜひ参考にしてみてください。
1.いきなり間取りを考えない
平屋は、周囲環境に恵まれた広い土地であれば、ぜひ自由なプランニングを楽しんでいただきたいと思います。
問題は、周囲を建物に囲まれている様な“都市型の場合”です。
いきなり紙に向かって間取りについて考えがちですが、まずは周辺環境に目を向ける必要があります。
以下では、平屋の間取りを考える際に注目したいポイントについてお伝えしていきます。
1-1.庭との関係を重視しよう

せっかくの平屋なので、地面(庭)との関係を重視したいところです。
庭というと「南側がいい」と思われる人が多いのではないでしょうか?
実は、必ずしも「南の庭」に囚われる必要はありません。
もちろん良い形で南に庭を作れるのであれば一番望ましいでしょう。ですがそうした良い方向が取れないケースが多いのも現実です。
そうした場合、「平屋」の特徴を活かす工夫をしてみましょう。
平屋は建物の背が低いからこそ、北側にも陽の当たる庭を創れる可能性があります。
また、もし北側道路なら、アプローチや駐車スペースを庭と一体的にデザインしてしまうことで、別々に分離するよりも豊かな敷地活用が期待できることもあります。
「でも北側だと陽差しが入らない暗い家になっちゃうよ!」という声が聞こえてきそうですが、次に“屋根“について検討してみます。
1−2.屋根(窓)を検討する

平屋は2階が載っていないため、屋根の自由度が高くなります。それはつまり天井の自由度も高いということです。
さらにいうと、天井の自由度が高いということは窓の自由度も高いということです。
例えば、屋根の形状を「段違い形状」にデザインすると、ハイサイド窓を設けることができます。またシンプルにトップライトという選択肢もあります。
こうした窓の採用によって北側であっても十分な自然光を取り入れることができ、暗くて困る心配はなくなるでしょう。
さらにこうした高窓、実は自然エネルギーを利用した通風や排熱効果といった温熱環境制御(パッシブ)にも役立てることが可能になります。
注意点としては、窓が高所にあるので清掃は大変です。建物の背が低いと言っても、よじ登って拭き掃除するのは割と大変です。
ただ、ハシゴで登っても2階建てほど怖くない=メンテナンスし易い、という点をメリットとして考えることもできます。
「自分でやるのはちょっと…」と思われるのであれば、信頼できる建築会社に定期的な点検を任せれば安心です。2~3万円程度で年に1回、窓以外も含めて掃除屋さんに入ってもらっても良いでしょう。
1−3.周辺環境に目を向けよう
間取りについて直接触れてきませんでしたが、ここで言いたいのは、いきなり間取りから考えるのではなく、周辺環境とのバランスに目を向け、豊かな空間配置を探してほしいということです。
無理に南側にこだわった結果、窮屈な南の庭を介して隣家の裏側を眺めて暮らすというのが果たして良い住まいになり得るのでしょうか?
条件と手法によってはもっと豊かな環境が形成できるかもしれません。
先ほどの北側道路で北側アプローチという条件。一見あまり良くないと思われるかもしれませんね。
しかし、実はその敷地は西側にも豊かさを望めるという場合、落葉樹と一緒に適切な計画を行うことで、豊かな眺めと共に夏場の西日対策もできます。
こうした考えは2階建てだと簡単にいかず、平屋ならではと言えます。
ぜひ南側じゃないとダメとお考えの方にも、こうした周辺環境への視点を幾らか採り入れて戴けたら幸いです。
60年以上本物の注文住宅にこだわり続けた
杉坂建築のノウハウを見る
2.家の内部について考える

周辺環境に目を向けながら、家の内部についても考えます。
平屋の30坪は階段スペースが不要です。このため同じ30坪の2階建てに比べると意外と広さの余裕があります。
例えば別荘などで、玄関から直接居間へ入ったあと、居間を取り囲む様に個室や水廻りを構成することがあります。この様な配置は廊下が省略出来るため各スペースにゆとりを生み、間取りの考え方の参考になります。
また30坪という広さの場合3LDK程度まででしたら計画しやすいですが、個室の考え方次第では4LDKから何とか5LDKまで可能になります。
先ほど平屋は屋根と天井の自由度が高いとお伝えしました。そうすると居室の立体的な活用も可能になります。部屋数を増やしたい場合、そうした立体活用も視野に入れられます。
ロフト空間は若い世代に人気があります。就寝スペースにしたり、普段使わないものを仕舞っておく事もあります。立体的に考える分、平面的な床面積を抑えることができ、部屋数の増加に対応し易くなるのです。
このほか、間取りを考える上で、まずは居住者にとって最もくつろげる空間を重視し、起点とします。
多くの場合「居間」あるいは「居間+食堂(+台所)」になるかと思います(ここではまとめて「パブリック」と呼びます)。
冒頭でも記しましたが、くつろげる空間はできるだけ外部との関係も良好に配置したいところです。窓の外には何が見えるのか、周囲の建物との関係は大丈夫か。そういった部分まで気にかけるようにしましょう。
2−1.キッチンについて
特に女性は台所(キッチン)を重視する方が多いのではないでしょうか。
台所は3度の食事以外にも備えている機能は多く、台所は暮らしの中心を担っていると言っても過言でありません。食を通して家族が保たれる考え方は、多様化した現代においても普遍性を持っていると言えます。
キッチンの形式として、「対面カウンター型」、「個別型」、「オープン型」、「アイランド型」の4つが一般的です。以下でそれぞれの特徴について説明していきます。
●対面カウンター型
 「対面カウンター型」は現在最も人気がある形態です。
「対面カウンター型」は現在最も人気がある形態です。
台所に立つ人とパブリックに居る人とのコミュニケーションが図り易く、家事を行いながらテレビを見る様な事も可能になります。
適度な連続感を持たせつつ、パブリックから台所内部が見えにくいというのも利点であるのが特徴です。
●個別型
 台所は厨房、いわゆる作業場であることを前提とし、そこが完全に見えない様にするのが主な考え方です。
台所は厨房、いわゆる作業場であることを前提とし、そこが完全に見えない様にするのが主な考え方です。
ただしこの場合、パブリックとの隔て方によってその度合いや暮らし方に変化を持たせる場合もあります。
完全に引戸で仕切る方法、戸は設けず雁行させた壁によって見通しを遮る方法、両面から使えるカップボードで領域分けするアレンジタイプもあります。
直接見えなくすることで、台所の整理に特別な気遣いをしなくても良くなりますね。
●オープン型
 オープン型は壁付け型ともいい、最近では少なくなっています。
オープン型は壁付け型ともいい、最近では少なくなっています。
ダイニングの一角に壁を向いてキッチンセットを据えるタイプで、昔の公団スタイルという印象も強く、少し古いイメージもあります。
ですが、空間をコンパクトに納められる事がメリットと言えます。
一方、調理スペースにこだわりたい人が採用するケースも多いです。
真ん中に作業台を置き、それを取り囲むように厨房設備を配置すると、プロ並みの空間がデザインできます。
思い切ってキッチンセットを家具の一部の様に考えてしまうこともできます。
額縁デザインされた木製扉のキッチンを中心に家具も統一させると、欧風田舎スタイルやカントリースタイルにもなります。
業務用ステンレスキッチンなどと共にスチールラックやアンティーク加工された木製キャビネットなどを置けば、ハードなイメージのモダンスタイルに。
台所が一体化される分、空間にゆとりが生まれるため、それをパントリーなどに転用すれば収納量もアップします。
●アイランド型
アイランド型はかなりモダンなスタイルです。
キッチンセットを延長して食卓カウンターにしたり、リビングスペースを省略してダイニングを充実させるなど、個性的なプランを考えることもできます。
但し部屋の真ん中にキッチンセットが配されるため、実は意外とスペースを要するスタイルと言えます。
シンクとコンロユニット全体を島状にする場合と、いずれかのユニットのみを島状に配置し他方を壁付けする場合の2通りあります。
尚、コンロは外壁側にあるほうが排気ダクトや汚れの拡散を最低限に出来るため、維持管理の点でメリットがあります。
2−2.動線の考え方について

台所が暮らしの中心的機能を担うとすれば、台所を取り巻く動線をいかに機能的にできるかが重要な要素となります。
間取りを考えるとき、どうしてもリビングの見た目やキッチンの充実に目が行きがちです。ですが機能的な配置が考えられていると生活してからのストレスが低くなるため、こうした部分へ注目も必要です。
特に台所はパブリックに最も近接しながら、ややプライベートに寄った空間とも言えます。
汚れやすく臭いも生じ、食材をはじめとしたストックからゴミまで多数の物に溢れるため、できれば他人に見られたくないのではないでしょうか。
また来客時に応対していない家族が、いちいち来客と顔を合わさずに台所へ入りたいなど。
そのため、来客に分からない様な動線も考えられれば安心です。
パブリックに繋がる動線とは別にもう一経路確保できると、そうした心配が解消できます。これは俗に言う「裏動線」です。
例えば、玄関ホールや廊下に面してパブリック用と台所用の2つの出入口を並べるケース。
あるいはマンションによくある間取りで、廊下から一歩入って台所脇を抜けるように奥のLDへ入るかたち。
この場合、台所は出入口を設けた壁で仕切られ、奥のリビングダイニングとはカウンター越しに対面します。
リビングダイニングよりも手前に台所を配することで裏をとれる。これもひとつの完成した間取りなのかもしれません。
機能動線は基本的に2つの方向から連携して検討すると良いでしょう。
1つ目は「内部動線」。
これは洗面脱衣室やユーティリティスペースとの関連が主で、「洗濯動線」とも言われます。
明快な領域分けと動線が確保できると、日頃の心理的負担を減らすことができます。また、空間を無駄なく配置することができれば設備配管類も合理的になる為、メンテナンスも行いやすいというメリットもあるのです。
もう1つは外部との繋がりである、いわゆる「お勝手動線」で、ゴミ出しのほか汚れ物、買い物、物干し場への動線などをいいます。
物干し場において洗濯物はパブリックから見えない方が美しく、周囲から見える部分への考慮が必要です。これは意外と全体構成に影響を与える要素にもなるので、あらかじめ考慮しておきましょう。
こうした動線との関係も考慮すると簡単にまとまらない事も多いかと思います。
そうした場合、屋外との中間領域の確保、トップライトをはじめとした窓の取りかた、格子やスクリーンを活用した相隣関係の調整など、様々な組み合わせも考慮しながら最も良い方法を見つけ出すようにしましょう。
・機能動線 [ 台所―ユーティリティ/パントリー(=勝手口)―洗面脱衣―ホール/廊下―玄関]
洗濯動線とお勝手動線、そこに収納を加え、それらを連携させた機能動線。
TPOに合わせた人の動きに基づき、効率の良い配置を考えてみてみましょう。きちんと領域分けしながら配置にぐるりと回遊性を持たせることで生活も楽になります。
スペースを取りやすい平屋であれば、そうした点にも注意した間取りができるでしょう。
2−3.寝室・個室について
寝室・個室は、特別な考え方がない限りプライベートな空間です。
個人的な時間を過ごす場所であり、個人的な所有物をしまっておく場所。
最も気兼ねなく安心できる場所とも言えます。
一般的な生活習慣に基づくと、「できれば」寝室にも朝日が入る窓が欲しいところです。
そしてもう1つ、風通し良い配置を計画するようにしましょう。
今は換気設備の義務化によって空気の淀みに対する心配はなくなりましたが、それでも季節によって自然の風が抜ける部屋は気持ちが良いもの。直接的な窓でなくとも、他の空間とを繋ぐ間仕切りを工夫したり、上下立体的に活用するアイデアもあります。
また、部屋の広さについても十分確認しましょう。
現在は布団よりベッドを用いる人が圧倒的に多くなっています。ですので寝室を考えるときは “ベッドがちゃんと置ける部屋のかたち”を考慮する事は重要です。
ベッドの大きさをちゃんと考え、周囲を人が歩いても支障無く、収納扉を開けて物を出し入れするのに支障の無い空間を確保します。そうすると、2人部屋なら正味7.5帖、1人部屋なら正味4帖以上を確保できると、寝室としては問題ないでしょう。

1人部屋の場合は子供部屋か夫婦別室の片部屋である事が多いので、デスクスペースを要する場合もあります。これを踏まえると正味4帖は割とぎりぎりで、5帖程度欲しいところです。
これらについては必ずしも最低限の広さではありません。もっと突き詰めることは可能であり、立体的な活用によっては3帖程度でも問題ないこともあります。
2−4.収納について
最後に収納についてですが、これは十分な正味スペース(実際に収納可能なスペース)を確保できるよう、よく考えましょう。
ここで注意したいのは、壁面クローゼットの奥行き寸法です。
特に男性用の場合、冬物の厚手ジャンパー、ダウンジャケットなどは幅を取るため、内寸60㎝~できれば65㎝は確保したいところです。もし難しければ手前に引き出すスライドハンガーを用いる方法もあります。
また扉もなるべく高さを大きく取れる物が良いでしょう。収納はやはり上部が使いにくくなりがちです。扉が高く、開ければ上の方まで見渡せる方が格納しやすくなります。
更にクローゼット扉の手前空間にゆとりが無い場合、開き戸より折れ戸、折れ戸より引戸の方が省スペースとなります。ただし引戸の場合、2枚または3枚と扉が重なると相応の厚みとなるため、収納内部の奥行きが狭くなってしまうことに注意が必要です。なお、扉の価格については「折れ戸>開き戸>引戸」という傾向があるので予算に合わせて検討することも忘れないようにしましょう。
60年以上本物の注文住宅にこだわり続けた
杉坂建築のノウハウを見る
まとめ
30坪の平屋の間取りについてどのように考えれば良いかをお伝えしました。
重要なことは「いきなり間取りを考えない」ということです。
住まいの快適性というのは、換気や断熱、使用する素材だけでなく、内外及び内部空間相互の組立て方によって使い易くなる事によっても大きく左右されるのです。
間取りを考えるときは、ぜひ広い視点で引いて見るようにしましょう。つ