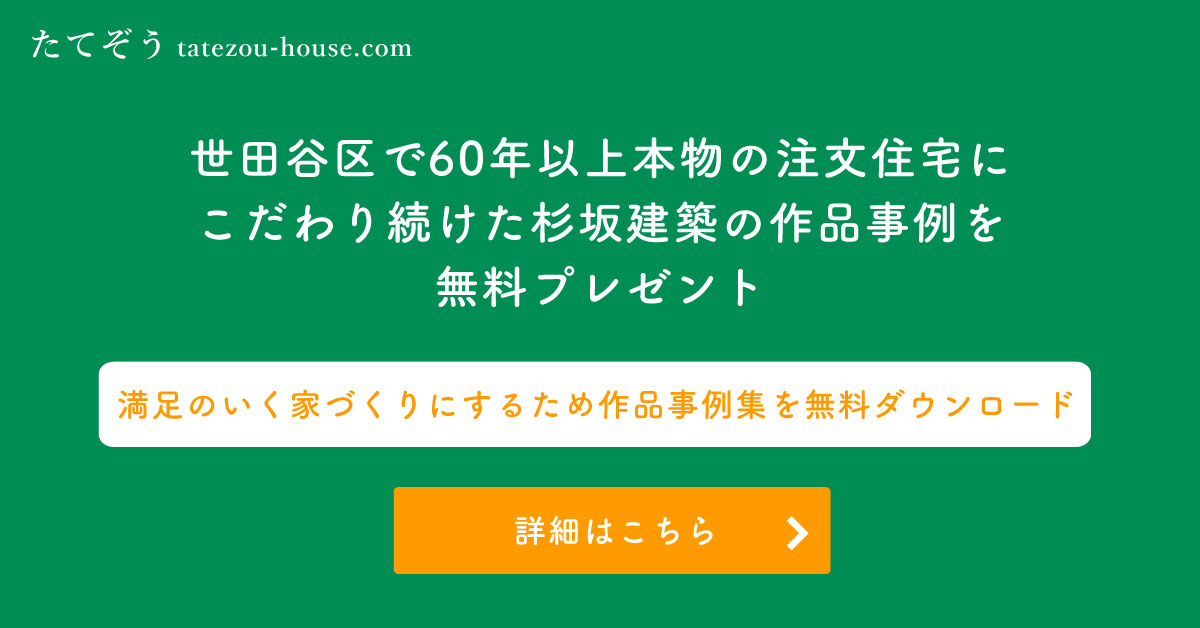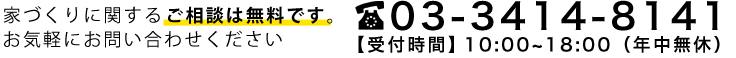家は何十年と住み続けるものです。
そのため今は問題なくても将来的に介護をしなければならなくなる事もあるでしょう。
また、現時点で高齢者や身体が不自由なご家族がいらっしゃる場合、今すぐバリアフリー住宅にしたいと考えている方もいるかもしれません。
快適で住みやすい住宅にするために考えておかなければならないバリアフリー対策は沢山あります。
今回は、バリアフリー住宅を検討しているのであればぜひとも知っておきたいポイントや費用、注意点などについてお伝えします。
1 バリアフリー住宅とは?
バリアフリー住宅とは、段差の解消、手すりやホームエレベーターの設置、廊下やドアの間口を広めに設けるなど、お年寄りや身体の不自由な方にとって障害となるものがなく、安全に暮らすことが出来る住宅を一般的に称します。
障害者・高齢者の為だけでなく、全ての人にとって安心安全に暮らせる家であるとも言えます。
このほか、家の中で温度差をなくし、ヒートショックなどが起きないようにする事もバリアフリーのひとつと言えるでしょう。
断熱性能をバランス良く与えることで熱の流れが効果的に生み出せたり、採光や通風がしっかり考慮できるとなお良いでしょう。
採光という点で言うと、高齢者にとって暗い部屋は足元が見えにくくなるので危険が伴います。光の採り方や照明計画、明度差を設けた素材選びなど、視覚効果を考える事もバリアフリーにつながります。
60年以上本物の注文住宅にこだわり続けた
杉坂建築のノウハウを見る
2 バリアフリー住宅で考えるべきポイント
バリアフリー住宅を考える場合、障害となるのが玄関、トイレ、廊下、浴室、階段です。
以下ではそれぞれのバリアフリーについて見ていきましょう。
玄関
日本の住まいは欧米と異なり、高さの変わる玄関が最初のバリアとなります。
●アプローチについて

最近は住まいのメンテナンス性能向上のため、しっかりとした床下空間を確保する事が求められるようになりました。このため、地面と1階床の高低差が大きくなりがちです。床下を無くした土間の家などもありますが、一般的ではありません。
ここをバリアフリー化する際、先ずは道路からのアプローチ(通路)について考える必要があります。
車椅子が問題無く出入りできるようにする場合、スロープの勾配として1/12から望ましくは1/15以下が確保できると良いとされます。
ただし、この勾配だと、例えば高低差50㎝を解消したい場合には通路として6~7.5mの距離が必要となり、両端に平らな場所を設けようとすると全長10~12mの通路スペースが必要となります。敷地にゆとりがあれば良いですが、現実的にこれは難しい事が多いでしょう。介助者がつく事を前提に1/10~1/8程度まで上げて考えることもありますが、それでも一定の距離を要します。
こうした場合、段差解消機の設置によってスペースの省略を図る対策がありますが、庭を回る別ルートを検討する方法もあります。リビングルームと床の高さを揃えたウッドデッキを設け、そこへスロープでアプローチするという考え方です。
●玄関の段差について
玄関の土間と1階床面の段差解消について、建築的にスロープを構築出来ると良いですが、計画時点での重要性や段差の大きさ等によっては、市販されている段差解消用の小型スロープ(置き型)を検討するのも手です。
このほか高齢者の使用を考えた場合、上り框の部分に手すりを設けると利便性が高まります。従来の玄関のような大きな段差を設ける場合、土間にスノコを置いて上り降りの補助スペースを設け、椅子やベンチを設けて靴の脱ぎ履きし易くするのも良いでしょう。こうした種類の介護用品(置き型)などもあります。
●玄関戸について
玄関戸はできる限り引戸が望ましく、軒(庇)を深くすることで降雨・降雪時には濡れずに家に入ることができます。
トイレ
トイレについてもいくつか検討すべき内容があります。
●幅について
車いすを考慮すると、トイレの幅は最低でも120㎝あることが望ましいです。
バリアフリー対応の施設などでは2m四方ぐらい確保され、その中に手洗スペースなども含まれています。戸建て住宅で同様のスペースがとれれば良いですが、住宅の規模によってはそれも難しい事があるでしょう。
一般的な住宅のトイレは1帖程度の大きさが殆ど。この寸法だと人が通るのに必要な幅(有効幅)と同じ80㎝程度となります。
そのような場合でも、便座に座ったとき両脇に手摺りやそれに代わる支持材(跳ね上げや置き型など)を設けられれば、利用者はもとより介助者にとっても負担軽減に役立ちます。
●ドアについて
通常、トイレのドアは外開きにするケースが多いですが、車椅子の場合外開きだと入りにくく閉めにくいです。
引戸は片引きよりも2本、3本引きと大きく解放できる仕様の方が動き易くなります。
引戸にできない場合は折れ戸のほか、開きながらスライド回転して引き込まれるドアなどもあるので、どれが設置可能か確認してみましょう。
●その他
 将来的な間取りを考えることも大切です。
将来的な間取りを考えることも大切です。
トイレが洗面所に隣接する場合、壁を耐力壁ではなく筋違いなどのない一般壁にしておくと、将来的に洗面所と一体化して広がりを持たせる事も可能になります。
ただし、それにとらわれすぎずに全体プランとのバランスも考えるようにしましょう。
廊下

日本の住宅は廊下の幅80㎝程度が一般的です。バリアフリーを考える場合、あと5~10㎝プラスするだけで広く感じることができます。
室内用車いすは幅65㎝程度のものが多いので、ある程度幅を取っておくことで直線を進むとき少し左右にぶれてもいくらか余裕がありますので安心です。歩行用の介助器具を使用する場合も同様です。
曲がり角は少ないに越したことはありませんが、あった場合でも少し広めにしておくと動きに余裕が持てます。
ただ、廊下の幅をリフォームで広げるのは難しい事も多いですので、これから新築する場合、可能な範囲で広めに検討してみてください。
その際、初めから手すりを設置しない場合、後から付けられる様に強度のある下地をつくっておく方法もあります。
リフォームの場合、古い家屋に見られる長い廊下でも、建具に付けられる手すりや脱着可能な手すりなどあります。専門家と相談してうまく活用してください。
他に、夜間でもほんのり明るく足元を照らしてくれるフットライトを設けると安心です。
コンセントを設けておき、災害時に懐中電灯として使えるLEDの常夜灯を取り付けておく手もあります。
浴室

浴室は水場であるため滑り易く、また裸になるため温度の影響を受けやすい場所です。様々な事故も多く発生しています。
そういった事を想定し、滑りにくさ、動きやすさ(伝いやすさ)、接触冷感を防ぎ保温性を確保するなど、様々な対応を考慮しておきたいです。
ひと昔前までは“在来浴室”というタイル張りの床・壁に浴槽を埋込むなど、職人さん手造りの浴室が多くありました。
水漏れ防止のため脱衣所と洗い場には段差が設けられ、低くなった洗い場に対して浴槽の縁が非常に高いなど、バリアが沢山ありました。
またタイルという冷たい素材と住まい自体の低い断熱性により、冬場は非常に寒い場所でもありました。
今では各住宅設備メーカーのユニットバスが非常に充実し、高齢者の安全も考慮して作られています。
設置できる手摺りのバリエーションも豊富で、滑りにくく冷たくない床や、またぎやすく一旦腰掛けられる様に縁を幅広くした浴槽など、バリアフリーのための様々な工夫が考慮されています。
脱衣所との段差もなく防水性も高いなど優れた点が非常に多いので、ご検討をおすすめします。
階段

階段は最もバリアフリー住宅にそぐわないと言えます。
バリアフリーには平屋建てが一番良いのですが、特に都市部では敷地にゆとりがとれず、2階建てでバリアフリー化を検討している方が多く見られます。
では、階段ではどのようなバリアフリーを考えれば良いのでしょうか?
●ホームエレベーターや段差解消リフトを検討
2階建ての住宅でバリアフリーにする場合、ホームエレベーターや段差解消リフト、階段昇降機など様々な機器がありますので、検討してみると良いでしょう。
階段昇降機は設置に際してかなり柔軟性が高く、後付けも可能です。少し費用が掛かるのが難点ですが、今すぐに導入しなくても良いのであれば、後から設置できる計画を考えておくのも手です。
また、ホームエレベーターは1畳なくても設置可能です。上下階で共通の広さを持った収納や、あるスペースの一角にエレベーターシャフトができても違和感の無い間取りを考えておくなど、ちょっとした一手間で不安が解消する事もあります。
●階段の勾配や登り下りのしやすさの改善
階段を設けるにしても、登り下りしやすい「寸法体系」というものがあります。
少しでも緩やかな方が良いのは当たり前ですが、緩やかすぎると段数が増えるとともにスペース確保に支障が生じる事もあるので、しっかりと設計士に相談しましょう。
また、折り返し階段を設ける場合、折り返し部分は回り階段とせず、できる限り平らな踊り場としたいところです。
らせん階段を想像いただくと分り易いかと思いますが、階段の中心に近いほど足を載せる部分が狭く危険です。折り返し部全体を平らにするのが難しければその半分に段差を設けるだけでも違います。
さらに「踏面」という足を載せる面において、考慮しておきたいことがあります。
まず、段の先端に滑り止め処理を行うこと。
木の段板の場合は先端に溝が切られていることが多いです。全体にウレタンなどの保護塗料を塗ると効果が出にくくなりますので、溝部分だけ仕上げ処理を変えるなど、対策を相談してみましょう。
そして廊下の部分でも触れましたが、フットライトのような足元を明るくする配慮があると安全性が高まります。
踏面或いは踏面の先端だけ色合いを変えるのも、視覚効果が上がって安全性が高まります。
住まいは色々な要素のバランスの中ででき上がります。
一つの要素に拘りすぎると全体が纏まりにくくなってしまう事もあります。
住宅は毎日使うものですので、住み慣れる事で解消できる問題もあります。
バリアフリーを考える際は、広い視点を大事にしながらできる限り採用していくということも考えてみましょう。
60年以上本物の注文住宅にこだわり続けた
杉坂建築のノウハウを見る
3 間取りの考え方

さらに、バリアフリー住宅は全体的な間取りの考え方も重要になります。
寝室とトイレの距離がなるべく近いと夜中も安心できます。
高齢者を介護する場合、介護者との気配が適度に分かりやすい配置もメリットとなります。
そのため間仕切りはできるだけ少ない方が望ましく、緊急時、早急に発見できるような間取りにするのも考え方の一つです。
また、部屋ごとの環境や日照関係も重要なポイントです。
例えば、寝たきりの高齢者の寝室は日当たりが良い方角に配置したり、大きな開口を通して屋外から出入り可能な仕様にするといった工夫は必要です。
細かな事ですが、個々の空間の中で手すりがより効果的に設けられる様に配慮する事もポイントです。
基本的には態勢(体勢)を変えるような箇所に設置するのが望ましく、玄関、トイレ、浴室などは空間も余り大きくないので、細やかに考えられていると大変楽です。
間取りのポイント
・寝室とトイレの距離を近くする
・間仕切りはできるだけ少なくする
・部屋ごとの環境や日照を考慮する
・体の動きに即した手すりの設置を検討する
60年以上本物の注文住宅にこだわり続けた
杉坂建築のノウハウを見る
4 バリアフリーにかかる費用について
バリアフリーを考えた場合、気になるのが費用です。それぞれの費用の目安については以下のようになります。
・浴室改修
現状のお風呂を解体し、使い勝手の良いユニットバスにした場合:100万~150万
・トイレ改修
便器の交換:30万~50万
・手すり設置
廊下やトイレに手すり設置:5万から10万(本数や手摺の長さにより異なる)。
間取りの変更や大規模なリフォームとなると、工事内容によって大きく費用は異なるため、一度見積もりを取ってみましょう。
介護認定で要介護もしくは要支援と認定されている方は、介護保険により工事費用の9割が支給されます。但し限度額は20万円で、1回の工事では最大18万までの助成となります。残り2万は次に工事を行う場合に利用可能となります。
支給対象となる工事は「手摺の設置」、「便器の交換」、「段差の解消」など様々です。
またバリアフリーの工事をする場合、申請者の状況によって自治体から別な助成が得られることもあります。各市区町村の窓口で相談することをおすすめします。
60年以上本物の注文住宅にこだわり続けた
杉坂建築のノウハウを見る
5 注意点
ゆとりのある敷地で新築するのであれば良いですが、小さい住宅で計画するとバリアフリーの導入そのものにバリアが生じがちです。
現時点で必要なのか、将来的に必要なのか、うまく代用できる機器や什器などないか、なるべく大きな視点で計画を捉えるようにしましょう。
将来的な対策がとれる様な下地造りなど、資金的なに低いハードルで準備しておけるものは業者にしっかりと聞き、採り入れられると理想的です。
バリアフリーリフォームの種類は多岐にわたります。
新築でしっかりお金を掛けるときとは異なり、補助金を加味しながらどこまでを採用するのか、家族としっかり話し合うことが大切です。
手すりの設置だけなら数万円で済みますが、浴室改修やホームエレベーター設置等は100万円単位の費用が掛かります。
また、今は設置工事の必要がない置き型の段差解消台や突っ張り型の手すりなども存在します。
そうしたものも活用し、ご家族が安心・快適に暮らすことが出来るよう計画しましょう。
60年以上本物の注文住宅にこだわり続けた
杉坂建築のノウハウを見る
まとめ
バルアフリー工事には、スペースボリューム、間取り、プライバシー、コストなどで一長一短あります。
計画を一緒に進める専門家にご確認のうえ内容や費用を理解し、バランス良く採用してご納得いただける住まいづくりを行なってください。